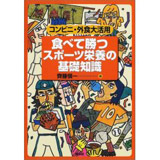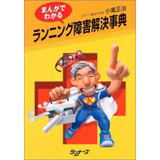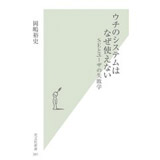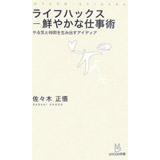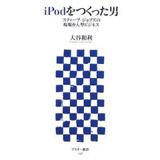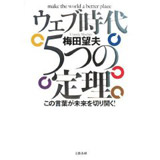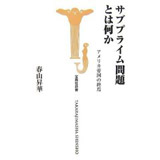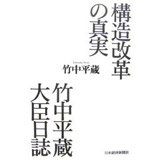「構造改革の真実 竹中平蔵大臣日誌」竹中平蔵・著。
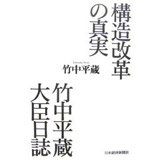
竹中氏が大臣時代に書いた日誌を元に書き下ろされた本。
竹中氏は大臣時代に相当に叩かれた。
私は、竹中氏が大臣に就任した当時、「学者に政治は無理では?」と思っていた。机上と実際は全然違います。そういう気持ちで見ていた。
大臣に就任していくらか時間が経過した後、サンデープロジェクトというTV番組で榊原英資さんが、竹中さんの事を「仮免をもらって路上に出たら、それなりになってきた」とかなんとか(細かいいい回しは忘れたが)、そういう事を言っていた。
その言葉を聞いた頃から、私も竹中氏の事を見直し始めた。
ところがその頃から、竹中氏に対するバッシングは相当に厳しいものになったと記憶する。私から見ても、それはいくら何でもひどいのでは?と思うようなバッシングが続く。
ところが、竹中氏は打たれても打たれてもへこたれない。まるでサンドバックのよう。一見すると、おぼっちゃん風のこの人の、どこにこんな強い力が潜んでいるのだろう?
そして、引き際も見事であったと思う。
その引き際を見て、この人の事が気になっていた。
この本は、大臣としての記録として大事なことが冷静に適切に書かれている。
私は「郵政民営化」には反対であった。
「あった」と過去形で書く。
この本を読んで、私が思っていた「郵政民営化」と小泉・竹中が思ったそれとに違いがあるように思える。マスコミが適切に報道していない事があるのかもしれないし、私自身も、きちんと理解しようとしなかった事に問題はあり、そのような誤解が生じる。
竹中氏は次のように書いている。
今後日本に、「ポリシー・ウォッチャー」と呼べるような専門家集団を作ることが不可欠だという確信を持つようになった。
小泉・竹中が描いたものが、その後の日本にどのような影響を与えるのか。それは時代が証明していくだろう。私は小泉政権には批判的な目で見ているが、「不良債権問題」を処理し、前に進めてくれたことは評価するし、それは竹中という人がいてこそだと思っている。