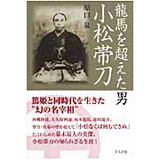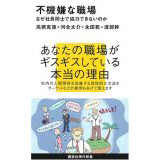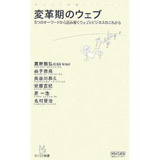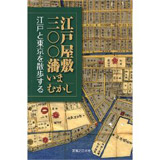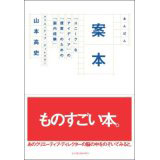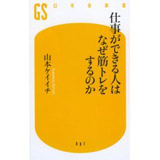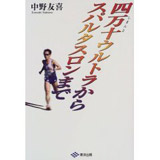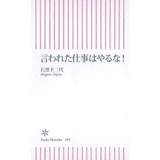NHK大河ドラマ「篤姫」を楽しみに見ている。
このドラマで俳優の瑛太さんが演じる尚五郎さんは、重要な役柄。
でも、この人はいったい何者なんだろう?と思っていた。
ドラマでは、尚五郎という名前から「帯刀(たてわき)」に変わったところ。書店でこの本のタイトルが目に入り、読むことにした。
この本によると、小松帯刀が果たした役割は大きく、坂本龍馬などの下級武士と、薩摩藩主などとの接点がこの人であったようです。
坂本龍馬と同じ天保6年生まれ。
「花の天保6年生まれ」と言われるほど、この年には様々な人が生まれています。
新撰組の土方歳三、会津藩主・松平容保、郵便の前島密、、、etc.
龍馬と帯刀は、もちろん接点があり(とうか親友であったと書いてあります)、龍馬が日本人初の新婚旅行をした人と言われていますが、鹿児島に案内したのも帯刀。また帯刀は、龍馬の新婚旅行の10年前に、父を伴ってではあるが新婚旅行に出かけている事実がある。
龍馬は日本初の株式会社・亀山社中を起こす事が出来たのも帯刀の力があってのこと。
明治維新の後、龍馬が生きていれば、、、という話はよくされるが、龍馬が作った人事の中に「参謀:小松帯刀」とあり、もし2人が生きていれば、と思うものである。
小松帯刀は35歳で亡くなる。
病気が悪化して亡くなったようだが、その病気が果たしてどういったものであったか詳しい事はわからぬようだ。
幕末という時代は、どこをどう切り取ってもドラマになりますよね。しかも登場人物が若い。若い力が国をダダーっと変えていった、すさまじいエネルギーの時代。そのエネルギーを爆発させるに至るには、徳川の江戸時代があったればこそ。徹底した身分制度があり、そうするとそれを打ち破ろうとするエネルギーが炸裂する。
時代のうねりから見ると、今この時は、どのような時になるのだろうか。もう少し先にいかないとそれはわからぬところもまた、歴史のおもしろいところです。