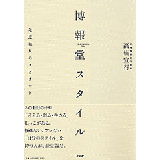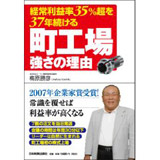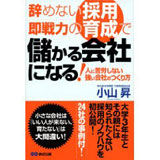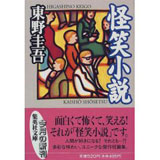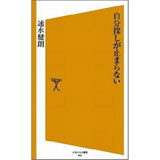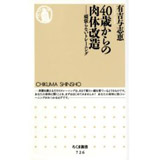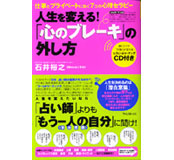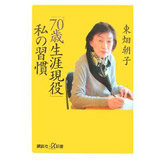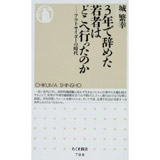「自分探しが止まらない」速水健朗・著。
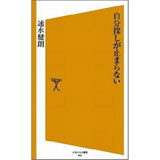
若い社員が送別会の挨拶で「自分探しのために会社を辞める」といったような事を話したことがある。
自分探し。
その言葉を聞いて、それはわからなくもないと思いつつも、小さな違和感を覚えた。その「小さな違和感」の正体がわからない。そんな折り、この本を書店で見て購入。
1ページを繰るごとに、私が持った違和感を丁寧に解説していてくれる。この本おもしろい。
そもそも「自分探し」がこれほどまでにとりただされるようになったのは?
だって、昔っから「自分探し」ってあったでしょ?
たしかに昔からあったのです。
古くは1960年頃ではないかと著者は書いている。
1975年の「俺たちの旅」というTVでは、若者3人が自分探しをしていた。それを中学生で見ていた我々世代にも、そういう暮らしがあることは知っていたし、実際にそういう暮らしの人もいた。私の亡くなった横浜の叔父もそうで、私や弟は少し憧れていた。
TVはその後も「自分探し」をテーマにしたものに人気がある。
「猿岩石」が「進め!電波少年」でヒッチハイクの旅をしたり、「あいのり」では本当の自分を好きになってくれる人を探して旅に出る。
自分探し。
昔からあったものを、なぜ、今、取り立てて言うのだろう?
著者は「中田英寿」が引退の際にサイトに掲載した文書を「”新たな自分”探しの旅に出たい」という部分を引用している。格闘家・須藤元気の引退にもふれる。
彼らの生き方に共感する若者が増えているのか?
自分探しには、内こもり(ニート)になるケースと、外こもり(海外に旅に出る)ケースがあるようだ。これらには自分探しビジネスとも呼べるものが出来ている。
今は心の時代と言われ、物よりも心を満たすものの方に需要がある。心を満たすビジネスが盛んになるのは、当然の事でもある。旅行においても、自分探しツアーといってもいいようなものが用意され、それに若者が集う。自分は特別かと思って参加すると、そのような若者が大勢いて辟易することもあろう。
自分探しのために定職に就かずに、あっちこっちで様々な経験を深める。その先にあるものは何だろうか?
日本の技術力は、一つの事をコツコツと長い年月をかけて形成していくものであり、あっちにフラフラ、こっちにフラフラする若者が増えていった場合には、その技術の継承がなされない危機感があるのではないだろうか?
自分探しにはまっていく若者の状況は少し見えた気はする。
その事が日本にどのような影響を与えるのかはわからない。それは注意深く見守りたいと思う。
私が思うのは、仕事をしながらでも、どんな状況においてでも、内面を見つめ続けていることは必要であり、それはことさら言葉に出して言うことではない。しかしながら「自分探し」という言葉が定着したことで、そのために会社を辞めたり、旅に出たりすることが半ば公認された気がする。そういうことに小さな違和感が残ったのかもしれない。
それにしても「自分探し」という言葉は、何か不思議な言葉だ。
「自分らしさ」を「探す」というよりは、「作り出す」方が言葉としては適切な気がするが「探す」という言葉にしたことで、そこには「元々、何かが存在」し、それを「見つけていないだけ」という解釈が出来る。
探している時間があったら、「自分の特徴を作り出す」ことの方が大事だと思うが、違うだろうか?