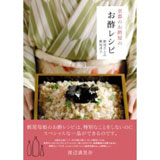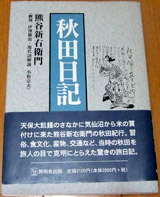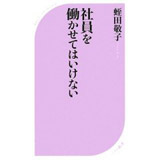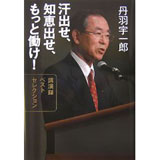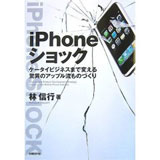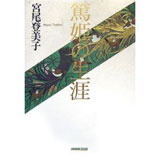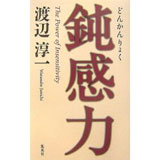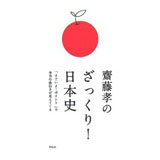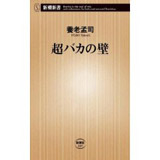
「バカの壁」は以前読んだ。
その本で「バカの壁」に気付き、その後の私の人生に少なからず影響を与えている。
「バカの壁」に比べると、はるかにはるかに読みやすい。
仕事というのは、社会に空いた穴です。道に穴が空いていた。そのまま放っておくと、転んで困るから、そこを埋めてみる。ともかく目の前の穴を埋める。それが仕事というものであって、自分に合った穴が空いているはずだなんて、ふざけたことを考えるんじゃない、と言いたくなります。
端から見ると養老さんは、自分に合った仕事を選び、それを楽しんでるように思ってしまうが、養老さんだって、このようなお考えを持つ。これを若い人に伝えたい。
若い人が「仕事がつまらない」「会社がおもしろくない」というのはなぜか。それは要するに自分のやることを人が与えてくれると思っているからです。でも会社が自分にあった仕事をくれるわけではありません。会社は全体として社会の中の穴を埋めているのです。その中で本気で働けば目の前に自分が埋めるべき穴は見つかるのです。
私は若い人が「おもしろい仕事」という時の「おもしろい」の定義は何でしょうか?と思うことがある。例えば「ワクワクすること」「やりがいがあること」などでしょうか?
それはどんな仕事でも、自分の思い一つで「ワクワク」出来て、「やりがい」を見いだすことは出来ます。つまり、「おもしろい仕事」というのがどこかにあるというのではなく、どの仕事にも「おもしろさがある」と私はとらえています。そのところを養老さんはきちんと説明してくださっているように思います。
「自分に合った仕事」なんてないと述べました。最近の人は「自分」について考えるのが好きなようです。だから「自分らしく」「自分探し」というフレーズもよく耳にします。
しかし自分とは何でしょうか。
この後がおもしろいのですが、気になる方は読んでみてください。