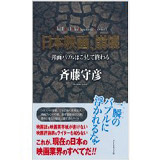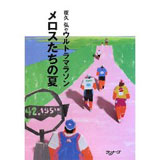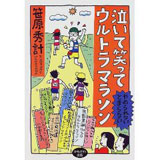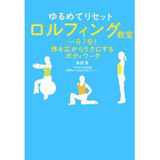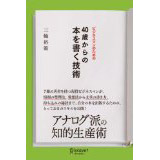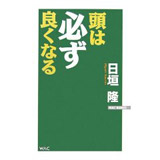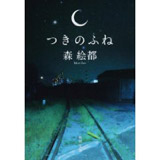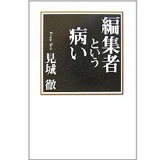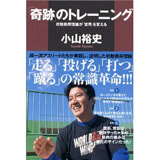「泣いて笑ってウルトラマラソン」笹原秀計・著。
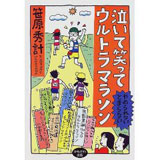
今年も6月のサロマウルトラマラソン100kmに申し込んでしまった。
普通はフルマラソンをそれなりの記録で完走して、さぁ、次はそろそろウルトラも走ってみますか、という流れになると思う。
しかし私の場合は、「北海道旅行」のつもりで「応援に行きます」と言ったのがはじまりで、「せっかく行くなら走ってみては?」という言葉に、それもそうだなと思ってしまう。
「50kmに申し込んでみようかしらん」と決意が固まったころに、「せっかくだから100kmに申し込んで、それで50kmで止めてもいいんじゃないの?」という先輩の言葉に、まんまと乗せられた格好で出場してしまったわけ。
案の定、、、60kmの関門に間に合わずに無念のリタイア。
リタイアしてみると、それまで100kmなんて途方もない距離だったものが、妙に悔しくなってきた。それで今年も申し込んでしまった。いまだフルマラソンもそれなりの時間で走れていないにも関わらず、だ。
その大会まで、あと3ヶ月を切った。
必死で練習する期間は2ヶ月(を切った)。
いまさら、何が出来るのだろう。
シューズを新調するか?
瞑想するか?
・・・
とにかく、本を読むことにした。
この本では、「サロマ100km」から始まり、「熊野黒潮130km」、「秋田内陸100km」、「山口100萩往還マラニックの250km」、「チャレンジ富士五湖117km」、「四万十川ウルトラ100km」、「えちごくびきの100km」に出場する経験談が書かれている。
はじめにウルトラを走り始めるきっかけとなったMさん、Hさんという仲間を紹介している。2人よりも練習量が多いのに、フルマラソンでは記録が出ない。良きライバルであり、良き仲間であったのでしょう。そんな思いから、サロマを走ることになったらしい。
そのHさんが、42歳の若さで亡くなってしまう。
四万十ウルトラでは、Mさんとともに、Hさんの写真をゼッケンに貼付けて走る。途中で「おにぎりがなくなる」(エネルギー不足に陥る)などとのアクシデントに見舞われ、何度も走るを止めそうになるが、Hさんの事を思い走り続ける。
たかがラン、されどラン。
走る人には、走る人ごとのドラマがある。
6月のサロマにも、さまざまなドラマが集まる。
元気を頂きました。ありがとうございます。
サロマ直前に、もう一度、読もうと思います。