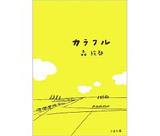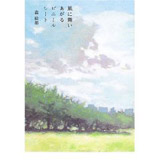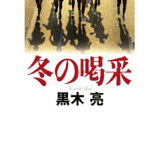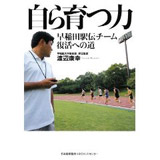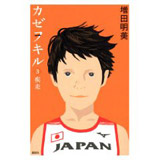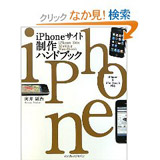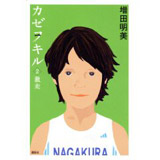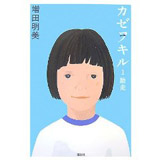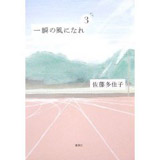「冬の喝采」黒木亮・著。
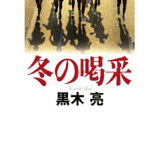
このごろ陸上に関する小説ばかり読んでいる。おもしろい。
この本は小説というよりは自伝的。
著者はかくべくして書いたというか、これを書きたかったのではないか? という「想い」が、本のあちらこちらから滲み出ている(気がする)。
主人公は、北海道の中学生の時から陸上を始め、高校1年ではそれなりの記録を出すものの、怪我に泣く。高校2年、3年は走れない。少し良くなったと思って走り出すと悪化するということの繰り返し。
いつも走れずに筋トレばかりを繰り返す。
大学は早稲田大学に普通に受験して入る。
陸上の思いは断ち切れない。東京の病院でギブスをかけて治すという方法を取り入れてから、少しずつ走れるようになる。
そうして陸上のサークルで1年を過ごす。すると「もっと走りたい」という欲求が出る。さんざん迷った挙げ句に、早稲田の競走部の門をたたく。
監督は、あの中村清さん。
1年浪人して早稲田に入った瀬古選手は同じ学年。
ただ、主人公の金山は1年遅れて競走部に入ったから、次の1年生と同じ扱いになる。それが入部の際の条件であった。
大学時代も怪我に苦しみ、「いつ悪くなるかもしれぬ」という恐怖とともに過ごす。それと、体重を増やしてはいけないので食事制限をする。「腹一杯食べたい」といつも思っている。
そんな陸上生活のかたわら(スポーツ推薦というわけではないので)他の学生と同様に授業に出て試験を受け、それ以外に「毎日英語を30分聞く」と自分に課して、実行する。ストイック。悲しくなるほどストイック。
中村監督は、陸上に対する情熱は人一倍あるものの理不尽だ。その理不尽さに「退部」も考えるが、瀬古さんにも思いとどまるような話をされ、結局、退部しなかった。
そのおかげと、本人の努力のおかげで箱根を走る。
冒頭の文章は、瀬古からタスキを受け取って走るという、曲で言えば、いきなりサビから入るような出だし。
分厚い本だが、グィと引きつけられて読んだ。
本当に陸上を辞めるのか?と聞かれた時に、
「僕は、、、瀬古にはなれませんから」と答える。
その1行は、身近に瀬古選手を見ながら辛い練習をこなした者でないとわからない、説得力のある言葉だ。
この本に出てくる「絵画館コース」と「迎賓館コース」というランニングコースは、私が時々走るコース。ここを瀬古さんが走っていたらしいという話はよく聞く。早稲田の競走部は、中村監督の家が千駄ヶ谷にあるということで、ここをよく走ったらしい。私はせいぜい3周走る程度だが、これをなんと10周、いやそれ以上も走る。しかも毎日。これはやってみた者にしかわからないハードな練習量。
著者は、1957年生まれ。
きっと、彼が4年の時に私が短大の1年生に入学したと思う。
私は、「なんとなくクリスタル」な女子大生としてチヤホヤされて大学生活をエンジョイしてしまった。わずか数年前の先輩は(たぶん同世代も、ちょっと下級生も)、安アパートに共同トイレ、風呂は銭湯という生活が当たり前であった。
そのようにして東京で勉強させてくれた事に、親に感謝し、そしてスポーツも勉学にも励む。そこにはチャラチャラした遊びはまるでない。たまに競走部の人達とハメをはずして飲む。おもいっきり飲む。
中学生の時に亡くなった伊東君への想い、両親への想い、いろいろな事がギューっと詰まった1冊。マラソンする方はきっと引き込まれます。お薦めの1冊。
ところで、マラソンに限らずスポーツをされる方は怪我に苦しむ。
私の弟は「おやま治療院(現在はおやま調整院)」を経営しています。本当に困ってる方は一度いらしてみて下さい。彼の治療は、悪い箇所を触るだけで痛みなし、マッサージをするのでもなし。ちょっと変わった治療です。私がこれまで怪我をしないでやってこれたのは、時々診てもらっているからなんです。