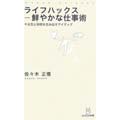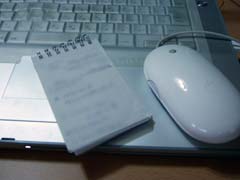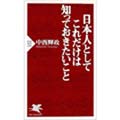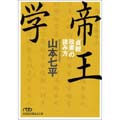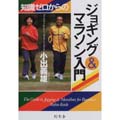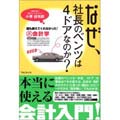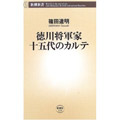「帝国ホテル 伝統のおもてなし」川名幸夫、帝国ホテル ホテル事業統括部・著。

私が過去2度(だけ)利用させて頂いた帝国ホテルのサービスは実にすばらしかった。1度は短大卒業の謝恩会、2度目は両親を宿泊させた時。
両親を宿泊させたのはラッキーな価格設定の時。2000年冬の日曜日に夫婦で泊まると安くなる「夫婦でのんびりサンデー」を利用。さらにもう一泊するともっと安い。2人の年齢を足して110歳以上の場合は眺めの良い部屋に泊めて頂ける、という嬉しいサービスだった。
今にして思えば、この時の東京旅行が両親への私の最大の親孝行だったのではないだろうか。なによりも帝国ホテルの優しいサービスが、私の代わりに親孝行をしてくれた。
足がだいぶ弱った父にホテルで車椅子を借りた。父の身体を気遣って、ホテルで過ごす時間が多い。ホテルで食事をとり、ホテルでショッピングをし、その先々で父の車椅子が通りやすいように、皆様に助けられた。その優しいサービスは私達家族の心に深く残り、もう東京に行くことの出来ないほど弱ってしまった父に、「また東京に行こうね、帝国ホテルに泊まろうね」と話すと、にわかに元気が戻ったものだ。
もう一度、母を泊めてあげたいと思うが、あんな安いサービスはその後、見当たらないので、私がしっかり稼いで、泊めてあげようと思うのであります。
その帝国ホテルのサービスは本当にすばらしい。それは次のような文書からも読み取れる。
(オールドインペリアルバーでは)二杯目からは、お代わりを承った時のグラスの位置を覚えておき、その位置に置きます。お客さまは、必ずと言っていいほど自分のグラスの位置というものをもっています。一杯目を標準位置に置いた後、その自分の好みの位置にグラスをずらすのです。バーテンダーはその位置を見逃さず、記憶します。
客室から出るごみはお客さまがホテルを出発された後、もう一泊します。
「お客さまとホテルスタッフの間には、丸太が一本あることを忘れるな」と先輩から教えられてきました。どんなに近しくなっても超えてはならない一線がお客さまとの間にはある。親しいからといって、立ち入りすぎてはいけない。程よい関係を保て、ということです。
この本にはそういった徹底したサービスが詰まっている。そしてこれが伝統として先輩から後輩へキチっと伝わっていることはすばらしい。なんとか母をもう一度、泊めてあげたいと思うのであります。