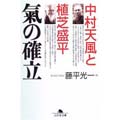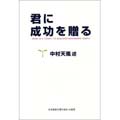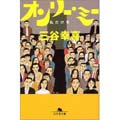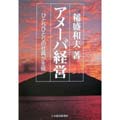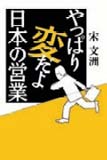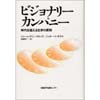先日・読んだ中村天風の書が印象に残る中、タイトルに引かれて購入。
合気道の創始者・植芝盛平と中村天風のいずれの愛弟子でもあったという藤平氏は、植芝氏から「リラックスする」ということを学び、中村天風の「心が身体を動かす」ことに学んだとのこと。「氣の研究会」の創始者でもある。
氣の呼吸法
1. まず肩を上下して、一番楽に肩を上下しやすい位置を探す。その位置で手を太ももの上に軽く置く。
2. 「あ」の口の形で口を開き、息を正面に向かってまっすぐ吐く。
3. 吐く息が十分に静まったら、上体をわずかに前へかがめ、残りのかすかな息を無理なく静かに吐き出す。
4. 体中の息を吐き出したら、わずかに前傾したまま、鼻先から息を吸い始める。
5. 足の先から順番に、腰、腹、胸、頭部と順番に空気が満たされるイメージを持つ。十分に吸ったら、上体を頭を起こして、また吐き始める。これを繰り返す。まずは一日15分でいいから、始めてほしい。