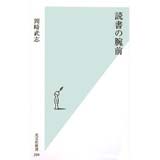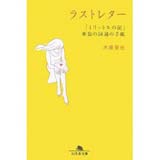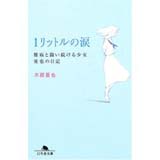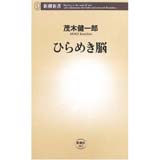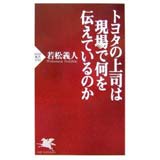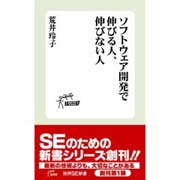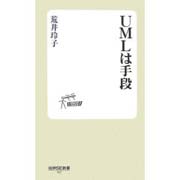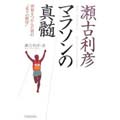「瀬古利彦 マラソンの真髄」瀬古利彦・著。
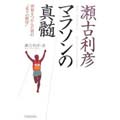
世界フィギュアスケート2007女子を昨日と本日TVで観た。
優勝を争う皆さんはまだ10代や20代前半っすよ。
トップアスリートの精神力は観るものを魅了する。
瀬古さんは、当時の日本マラソン男子を引っ張っていた。宗兄弟というライバルと伴に表彰台の高いところにいた。
端から見るとわからない苦悩が、この本にはたくさんある。それは驚きの連続とも言える。
元々は「野球の選手になりたかった」そうだ。中学では野球部に所属している。たまたまた中学校のマラソン大会で(負けるのが悔しいから走る練習をして望んだところ)3年間連続で優勝。それで「市の陸上競技会」に助っ人として参加したところ2000mで優勝。野球は肩をこわして断念せざるを得なかった。
もう野球ができない自分には、陸上しかない。
四日市工業高校時代は、インターハイでは800mと1500mで2連覇。5000mでも2位という成績。
私が瀬古さんを知ったのは、あの早稲田大学のユニフォームを着て走る姿。箱根駅伝では区間新を出し、モスクワオリンピック代表にも選ばれた。順風満帆だと思っていた。
しかしながら瀬古さんは高校卒業後、一般入試で早稲田を受験し、失敗して一浪している。そんな事は知らなかった。いろいろな挫折から始まっていたわけで。
しかも、、、高校時代には「あまり練習しない瀬古君」だった。だからマラソンのような忍耐力を伴うような種目は自分には無理だ、と考えていた。長い距離を走ることが苦手で1500mの選手になろうとしていたのに、早稲田に入ると「君はマラソンをやれ」と言われて「ハイ」と即答してしまったことから、マラソン人生がスタートする。
人生って、わからないもんですね。
最初のフルマラソン大会「京都マラソン」では、2週間前から先生に「餅を食え」と言われ体重が3kg増えた状態で望むという、先生も含めた全員が「マラソン初心者」だったという話。
自分用のスペシャルドリンクなどは用意してなかった。真夏の練習中でさえ水を飲んだことはない。喉が渇いても我慢。水を飲むのは練習が終わってからというのがお決まりで、給水の必要が説かれていない時代だったのだ。
1977年の話ですよ。今から30年前はこういう時代で、そういったところから瀬古選手はスタートしていたのかと思うと、頭が下がる。
その頃に宗兄弟の練習スケジュールを雑誌で見て驚き、刺激を受けて、ジョグの時間を少しずつ増やしていった。
冒頭の「はじめに」の部分で瀬古さんは次のように書いている。
これまで私は、マラソン練習のノウハウや練習メニューは「企業秘密」として、一般に公表したことはなかった。だが、男子マラソンの活性化を願って、ここにすべてを明かす決意をした。それが、今まで陸上界で育てていただいた私の義務だと思っている。