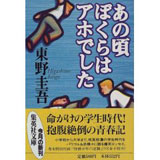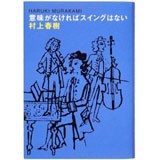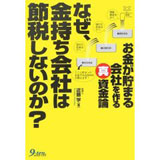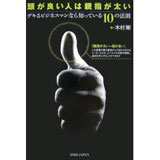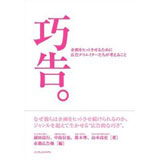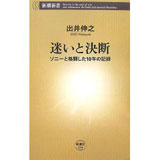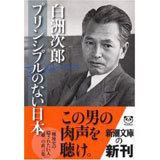まえがきに次のような記述がある。
ウェブ2.0は一見したところ、真のIT革命への力強い一歩であるように思えます。(中略)しかし、同時に、そこには米国発の文化独特の、楽天主義とうらはらの暗部もないではありません。一般ユーザー中心の民主的平等主義という美名のもとで、実は逆に、ITを使いこなせない中高年は切り捨てられるのではないか、わずかな成功者が途方もない巨利を得るかわりに貧者は巧みに搾取され、社会的な格差がますます広がっていくのではないか、といった懸念です。
「ウェブ礼参論とバカの壁」の章に、ウェブ礼参には、アメリカ流の楽天主義がはっきりとみとめられると書いていて、警鐘を鳴らしている。
どうなんだろう? そういう事は、使う人は、薄々(いやもっとハッキリと)わかっているんじゃないかしらん?
情報は小包のような実体ではない
「情報とは何か?」日頃、使い慣れた「情報」という言葉の意義を再確認し、そうね、私達はある一部分を切り取って、Webでビジネスをしているに過ぎないことを意識させられる。生命あるものは、皆、何かしらの情報を得て生きている。人間だけが情報を持つのではないし、もっと言えば、「ITがなんぼのもんじゃい」だ。そういう刺激(ちょっと立ち止まって考えようよ)は随所にある。
梅田氏の本を読んだ後は、こちらも読んでみると、さらに自分の考えが確立されるんじゃないかな。
西垣氏は、若い頃にスタンフォード大学で学び、アメリカ文化にふれ、とても楽しく過ごした事や、自身もGoogleを実はよく使うことも記している。だから、一方に偏っていくことに警鐘を鳴らしていいるのだ。便利なものは便利。だが、落とし穴もある。
この本は、いろいろな方向に話が飛ぶので、読む方もしっかりと付いていかねばならぬのだが、教育について渡部信一氏の言葉を引用した箇所がある。
東西文化の相違は、伝統的な教育方法の違いにはっきり現れます。教育学者の渡部信一によれば、両者はそれぞれ、「しみ込み型」と「教え込み型」と位置づけることが出来ます。
「しみ込み型」は、日本伝統における「わざ」の習得過程で用いられるものです。(中略)義太夫にかぎらず、「習うより慣れよ」とか「わざは兄から盗め」といった教育方法は、日本のあらゆる伝統分野に共通しています。(中略)
一見すると、「しみ込み型」は「教え込み型」より効率の悪い教育方法のように思えます。(中略)しかし、本当に身についた知、知恵にめで高まる知は、「しみ込み型」で習得するほうがよい、という気がしてなりません。
私もそう思います。