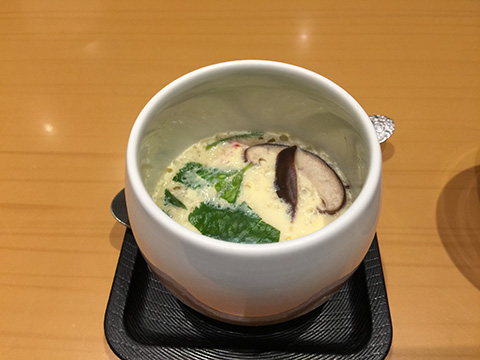GWのお休みは本日までです。
特に何をしたということもないが、ゆっくり出来ました。
ランチは、新中野の「赤坂屋」さんでラーメン。
私は「魚だし」を。美味しいです!

それから新宿に移動して、いつも病院のあとに休んでいる「カフェラリー」へ。
ケーキセットを頼んでみました。美味しいです。

昨日は久しぶりにガツっと走ったので筋肉痛です。
本日はゴールデンウィークの休日。
ランチは中野坂上の「ドナ」さん。
会社の近くに韓国料理店があります。
「百済」です。
今日はそちらでランチを。
美味しい。

「片岡球子展」を観に行った。
「東京国立近代美術館 企画展ギャラリー」で、5/17までやっている。
リハビリを兼ねて歩きます。
ダンナと四谷駅近くでランチをした後は一人で移動。
普段は歩かない道も歩いてみます。

この絵を新宿駅近くで見て、今日は来ました。1400円を払って中へ。

堪能しました。
絵を見るのって、いいですねぇ〜!
会社の近くにあるタイ料理店「サームロット」、時々、ランチに行きます。
いつもカレーを頼んでしまうので、今日は別の人が頼んだものを「私も」と便乗してみました。
美味しい。
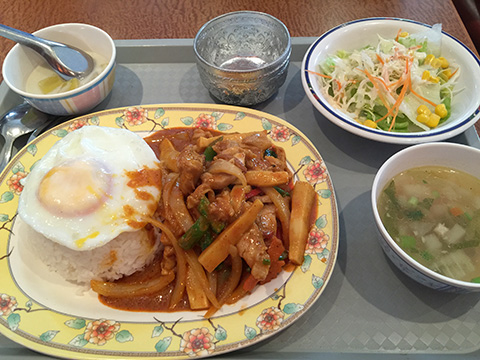
週に一度程度、ランチにお寿司を食べてます。
「すしまみれ」さん。
これにお吸い物がついて1,000円以下で食べられる。嬉しい。