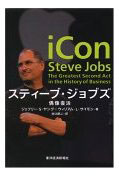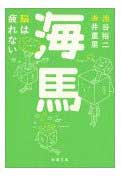「ザ・プロフェッショナル」・大前研一・著

大前氏の本は初めて読んだ。評判が高いが、正直言うと、少し拍子抜けしている。当たり前のことが多く、特に目新しさを感じないでしまった。私の読みが浅いのかな? まぁ、それでも、私にはおおいに参考になる。
顧客に対してやらなければならない仕事を100とした時、部下がやれるレベルが X だったら、「100 – X = 自分の仕事」と心得ている人が真のマネジャーです。
なるほど、この定義はわかりやすい。
テレパスの従業員は若い。若い上司に若い部下がつくので、やりにくいだろうと思う。若き上司に対する私のアドバイスも明確ではないな~。これを参考にしたい。
プロフェッショナルはいつも顧客のことを考えなければならないのです。
私がいつも言ってることと同じ。私が言っても説得力が欠けるが、大前先生が言ったとあらばと、納得してもらおうかな(笑)。おっと、さらに続く。
マッキンゼーにおける規律とは、繰り返しますが、「顧客を最優先に考え、最高の価値を届ける」ことです。
「マッキンゼーの規律」と私が言うことが同じとは嬉しいが、え、これって当たり前のことでしょ? あー、でも次が違うのね。
この規律とは「up or out」すなわち「昇進しない人間、伸びていない人間は去れ」というものです。
くは~、厳しい。この厳しさの点で私は劣る。私って優し過ぎ(笑)マジで。
毎年20%が退社するわけですから、同期の桜が100人いても4年後には20人になります。これがルールであり、顧客に迷惑をかけない唯一の方法だということを知っているからです。
なるほど。
ビジネス・プロフェッショナルに「妥協」の二文字は厳禁です。
テレパスには「妥協しないヤツ」がいる。彼は自分に厳しいが、人にも厳しい。私にも厳しい。が彼の仕事っぷりには感心する。私も見習いたい。
マッキンザーの議論では「What’s new?(何が目新しいのか)」、「So what?(それがどうした)」というフレーズが飛び交います。
構想する力、議論する力の大事さを書いている。
そもそも「discuss」という言葉は、否定を意味する「dis」と、恨むという意味の「cuss」が合体した言葉です。要するに反対したり反論したりしても「恨みっこなし」というのがディスカッションの本来の意味なのです。
GEの元会長・ウェルチの話など興味深い話が続く。あとは本を読んで下さい。当たり前だが大事なことがたくさん書いてある。
IQとEQ、あるいは左脳と右脳の相互作用という第三の領域について考える必要があると私は思っています。つまり、左でも右でもない新しいものを考えつき、かつ事業を創り出す能力、EQもIQも超越した総合力としてのプロフェッショナルな人物像ーこれこそが、21世紀の見えない世界を切り拓く能力です。
近頃の「マンションなどの耐震強度偽装問題」でプロらしからぬ一級建築士の仕事っぷりを聞くにつけ、「プロとは何か」を再確認するためにもタイムリーな本。