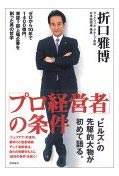著者は、日商岩井(現・双日)社員だった1991年当時、伝説のディスコ「ジュリアナ東京」を企画・運営し、退職後は「ヴェルファーレ」をオープンさせる。そしてグッドウィル株式会社を起業し、株式会社コムスンを傘下におさめ、グッドウィル・グループ株式会社のCEOとして成功する若き経営者。六本木ヒルズにオフィスをかまえるヒルズ族。私と同じ1961年生まれ。
この華やかな経歴から想像したものとは裏腹に苦労があった。
父親の会社が倒産すると、それまでの坊ちゃん育ちから一変して、生活保護を受けるまでの苦しい生活を経験する。
中学生の時には高校生と偽ってアルバイトをし、高校は「陸上自衛隊少年工科学校」に入学し、厳しい訓練を受けながら勉強をする。給与が出るので、それを家に仕送りをする。著者は貴重な(そして少ない)自由時間に猛勉強をし、防衛大学校に進学する。「ジュリアナ東京」からは想像出来ない経歴の持ち主だった。気仙沼でヌクヌクと生きていた私は複雑な思い。
著者は成功は「運が良かった」のではなく、なるべくしてなったと言う。著者が「センターピン理論」と名付ける理論があって、ディスコのセンターピンは「いつも賑わっている」こととして徹底した。そうして大成功へ。
しかしながら、「ジュリアナ東京」が大成功したにもかかわらず、著者は4000万円の借金を背負うことになる。その借金は7000万円にまで膨らむ。普通ならば、ここで挫折するだろう。しかしながらこれを乗り切るところがすごい。
コムスンは、13の拠点から一気に1200までに増やすことに成功した。その「スピード」については「完璧症候群をなくす」としている。9割出来てから次へ行くのではなく、7割の出来で次へ進むという理論。他にも随所に「スピード」に関する考え方がある。
著者が「介護ビジネス」に参入した時に「(あのジュリアナ東京の人が)それは、またどうして?」と思ったが、それは父の介護にあった。私も経験したが、介護が必要な人であっても、(家族以外の)他人の前ではシャンとしようとする。家族には甘えてしまう。家族は介護による疲労が蓄積され、悪循環に陥る。「介護をビジネスにするのは難しい」言われるが、介護ビジネスは必要なことだと私も思う。いろいろと考えさせられる1冊だ。