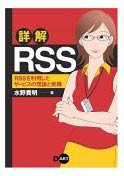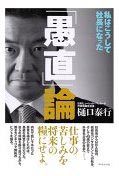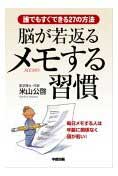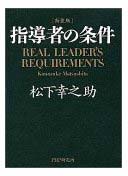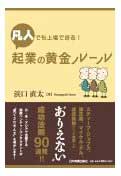「ゴールドラッシュの「超」ビジネスモデル」野口 悠紀雄・著。
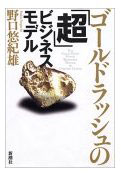
うわっ、これ、おもしろい。
第1部:19世紀のカリフォルニアで起きたゴールドラッシュ、第2部:鉄道王リーランド・スタンフォードによるスタンフォード大学の設立、第3部:シリコンバレーの起業家たちとIT産業の発展、という流れになっている。
19世紀、ゴールドラッシュで大富豪になった人達は、意外にも「金」で儲けてない。西部に流れてくる人達に必要なものを、先に買い占めておいて高く売る。先見の明とタイミングの良さで大儲けをする。ところが、大儲けをした人が最後まで幸せかというと、またそうでもなかったりする。そのお金で次の仕掛けをして、一文無しになってしまったりするわけだ。
さらに、、、大富豪になって幸せに生きた人達の中でも、後世に名が残っている人はほとんどいない。大学を創設したスタンフォードなどの限られた人だけだ。それはほんの150年ほど前の話なのに。
当時と「今」は似ている点が多い。アメリカでは、新しいIT企業が出来ては消えていく。そのほとんどがスタンフォード大学を中心としたシリコンバレー界隈の話だ。そういう土壌が作られたのは、19世紀のゴールドラッシュのおかげだ(それまで、その地には何もなかった)。
著者の野口さんは、日本への警笛を鳴らしている。19世紀のアメリカでは東部からカリフォルニアに向かうにはは荒野を越える危険な旅だった。日本から船で向かった方が楽だったのではなかろうか。けれども当時の日本は鎖国で、海の向こうで何が起きているのか知らなかった。もしくは知っていても、日本とは別世界の話だったろう。
では、21世紀の現代はどうか。海の向こうの話はおもしろいほど伝わってくる。けれど日本の、私達の動きはどうか? 新しい産業を生み出すパワーはどうか? いろいろと考えさせられる本だ。