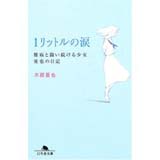ドラマに涙した「1リットルの涙」を読んだ。
ドラマ以上の感動。
昨日のマラソンに行く道中で読み始めて、電車の中、ジャージを着たおばちゃん(私)は泣きそうだった。
健常者にはわからない、いろいろな事が、こんなにたくさんある。
まわりの人の、ほんの些細な言葉がかくも傷つけてしまう。
私の父は60代半ばで脳梗塞を煩い、半身(特に足)が不自由になってしまった。父はその病気になる前は優しくて、穏やかな人だったのに、病気になってからは些細な事に苛立ち、周囲(特に母)に当たった。そのことが家族を驚かせた。
以前出来ていたことが出来なくなってしまう悲しさを、私達家族は、頭では理解しているつもりが実際には理解出来ずに、父を苛立たせてしまう。そのことを本を読んで思った。
最近、政治家として立候補する方々は「福祉・福祉」と口々に言う。
普段のその人の行動を見ていれば、本当に「福祉」を思っているのかはわかるというものだ。
身体が不自由な人が「明るく生活できる社会」は、物が整ったところで、精神がついていかなければ成り立たない。そういう教育を大人も子供も一緒になって考え、実践していくほかはない。
以前、新宿駅で、車椅子の人に山の手線の乗り場を聞かれ(当時はエスカレータがなかったので)「ここです」と階段の上を指差す。その方は、上を見上げて、途方に暮れた。私は通りかかった駅員さんに「山の手線に乗りたいそうです」と伝えるも、駅員さんも人手が足りずに困っている。それで私は思い切って「すみませーん、どなたか手伝ってください」と声を張り上げた。すると、サっと、4〜5人の男性が集まり、駅員さんとともに車椅子を抱えて階段を上がってくださったのだ。
それは本当にあっという間の出来事で、驚きと感謝が一緒にやってきた。
手伝ってくださった男性は、いずれも中年の方々だったことを覚えている。
車椅子が倒れないように、気をつけて、優しく運んでくださる。
私は何も出来なかったが、一緒にホームに上がっていった。
手伝ってくださった方は、皆、いい表情をしていた。
そういう人達の手で、日本はもっと優しい国になれる。
今は元気な私も、いつ、皆様のお世話になるかわからない。
高齢化社会には、皆で助け合って生きていくほかないのだ。
それにしても、著者の亜也さんは、すごい人です。