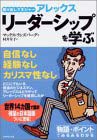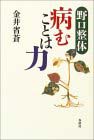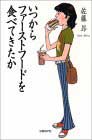「最強の経営手法TOC」山中克敏・著、加藤治彦・解説。

「ザ・ゴール」を読んで「TOC」の事が少しわかった気がした。「ザ・ゴール」のあとがきに、その本通りに実践して成功した例がいくつもある、と記述されているが、「そんなにうまくいく?」と勘ぐっていた。
「まぁアメリカではうまくいったかもしれないが、日本ではどうだろう?」とも思った。
ネットで「TOC」を検索したら、この本(最強の経営手法TOC)がヒットした。読んでビックリ。
著者は、オキツモ株式会社の創業者の息子さんで、現在、会長職を務める山中氏が執筆している。内容はオキツモで起きた実際の出来事を物語風に、そしてわかりやすく、TCOの導入から成果が表れる様を書いている。
驚いた・驚いた。
なにが、って、今は改善されたとしても、数年前までは「納期の遅れ」や、諸問題をかかえていて、それを会長自身が文書にしていることだ。自分の会社がかかえていた問題点を本にするというのは勇気がいる。さらに、成功していく課程を文書にしている。「よそにまねされる」と思って隠したくなるのが普通ではないだろうか。山中会長の器の大きさを感じる。
オキツモがTCOを取り入れ、試行錯誤を繰り返しながら、社員の意識が変化していく様子がわかりやすい。最初、現場は「上が余計な事をはじめて、、、」と思うし、これまでのやり方を変えるというのは、本当に難しい。そういった「日本企業の文化(風土?)」を踏まえているので、私には「ザ・ゴール」よりも身近な例でわかりやすかった。
我々とは異なる業界ではあるが、業務を進めていくうえでの「遅れ」また、その原因となる「クライアントからのとびこみの急ぎ仕事」等など、共通する点がある。製造業のことはちっとも知らなかったが、問題の根本というのは共通するのかもしれない。製造業ではない分野の方も参考になる本だと思う。
山中氏の経営者としての才覚はすごい。
「日経ビジネス」の記事で「TOC」について知り、「うちの会社にいいんじゃないかな?」と言い出したのは山中会長だ。また、父親の病気という事態で大学を中退したので、会長になってから復学し、大学院まで出ている。その中で「経営手法」について学ぶ姿勢にも頭が下がる。さて、こういった事を私の会社ではどう活用したらいいのかな?