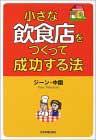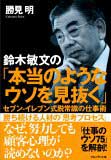弟から借りた。おもしろい!
小説仕立てで、楽しみながら「ブランド」について理解出来る。難しいビジネス書と違って身近な題材と、ごく普通の登場人物など、設定がいい。文体は読みやすい。
開店して3ヶ月目の売れないおにぎり屋さんが舞台。
ふとしたアイディアからどんどん「売れる店」になっていく。
現実はそれほど簡単ではないだろうが、でも、やれば出来そうな気にさせる。
「コンセプトの構造」を図で説明している。上から「コアバリュー、パーソナリティ、ベネフィット、ファクト」という階層に分けられる。
コアバリュー:ブランドが顧客に提供する価値の核心。
パーソナリティ:ブランドを象徴する人物の人格(個性)
ベネフィット:ブランドが顧客に提供する具体的な便益
ファクト:パーソナリティとベネフィットを実現するための事実(仕組み)
弟からは「これを読んだらおにぎり屋さんを開きたくなるかもよ」って(笑)
終盤に気づいたのだが、著者は株式会社マインドシェアの方だ! テレパスはマインドシェアさんと取り引きがあるので、驚いた。