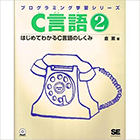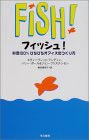「すべては一杯のコーヒーから」松田公太・著。

タリーズコーヒージャパンの創立者/松田氏が書いた本。
設立から数年の間にナスダックジャパン上場を成し遂げた若き成功者は順風満帆に見える。しかしながら、この本を読むと、それまでの苦労は数知れない。
私も設立の経験を持つから、経験不足による様々な失敗談は、あまり語りたくないこととして封印していることも多い。けれど著者はそれを隠さずに書く事で二度と同じ失敗を繰り返さないようにと、そして、これから起業しようとする人へのアドバイスになればという思いは、すばらしいのひとことに尽きる。
著者は、小学校から高校までのほとんどを外国で暮らした帰国子女である。日本語の他に自由に外国語を操れる帰国子女をうらやましく思うものだが、子供の頃から別の文化に触れることの難しさがあるわけで、それを一つ一つクリアしていった先の成功だろう。
英語を自在に操り、アメリカの文化に慣れ親しんだ著者でさえ、タリーズコーヒーUSAとの契約については四苦八苦している。契約書の記述内容の持つ重要性を改めて思い知る。日本では、今だに「なーなー」で済ますこもと多い。
この本は2002年に書かれていて、まさか2004年に上場企業している複数の会社にいろいろな問題があることが公になるとは思わなかっただろう。2002年当時、著者は持ち株比率についての考え、上場するということの意義を明確に持っている。
オーナーが半分以上の株を持ち続ける「おやかた体質」とは全然違う上場企業としての会社のあり方については、勉強になることも多い。
近頃は「起業してから何年で上場した」ということが華やかな話題として取り上げられるが、企業にとって上場する事が最終目的ではない。それが持つ本来の意義を考え、それがふさわしいのであればそうすればいい。そうでなければ違う道もある。起業に興味がある方には、特にお勧めの本。
本の感想を書き終えてからインターネットで検索すると、タリーズコーヒージャパン株式会社は、その後、 フードエックス・グローブ株式会社のグループ会社として、次のフェーズに入ってるようだ。松田氏は緑茶を専門にしたお店「Koots Green Tea」を展開するなど、その勢いは衰えない。そして、驚くのは、2004年1月に経営戦略を理由に上場を廃止していることだ。2002年の執筆時から現在に至まで、著者は相当なスピードで駆け抜けているのだろう。是非、この本の続編を出して欲しいものだ。