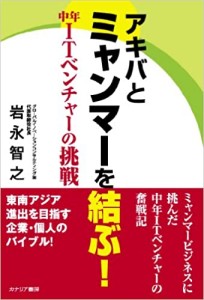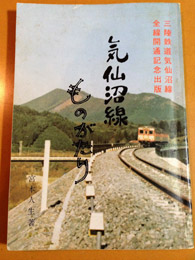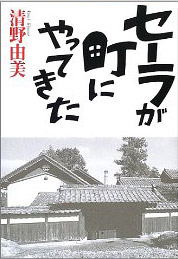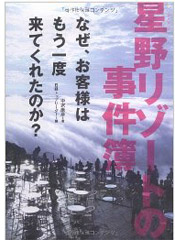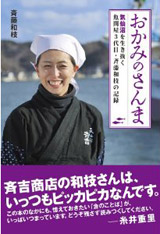「気仙沼」高村光太郎・著。

Kindle買ったら読もうと思っていたのが、この本。
Kindleで「0円」です。
9月に行われた「第3回気仙沼フォーラム」で川島先生から、この本の話を聞いていて、読みたいと思っていたのです。それが0円ですから。
高村光太郎は、昭和6年8月に三陸地方を訪れている。
その際に、気仙沼にも立ち寄った。
気仙沼は昭和4年に大火があり、魚町、南町、八日町などの旧市街地を焼きつくした。川島先生から見せていただいた当時の写真は、まるで、今回の大震災跡のようでした。いや、もっとひどい状態だったかもしれない。
昭和6年に高村光太郎がいらした時は、まさに復興の最中。
本の冒頭は、
「女川から気仙沼へ行く気で午後三時の船に乗る。」
当日、気仙沼に入るには船を利用することが多かったようだ。
そして、「岩井崎から奥深い気仙沼湾にはひる。」とある。
「午後七半。」
その印象は、
「船から見た気仙沼町の花やかな灯火に驚き、上陸して更にその遺憾なく近代的なお為着せを着てゐる街の東京ぶりに驚く。」とある。
「夜になれば鼎座に浪花節(なにはぶし)があり、シネマがあり、公娼が居なくて御蒲焼があり、銀座裏まがひのカフエ街には尖端カフエ世界、銀の星、丸善がある。」
高村光太郎は「柳田國男先生の「雪国の春」といふ書物をかねて愛読して」いて、「気仙沼あたりに来ればもうそろそろ「金のベココ」式な日本の、私等の細胞の中にしか今は無いような何かしらがまだ生きてゐるかも知れないなどと思つてゐた。」
その期待とはうらはらに、気仙沼は賑やかしい街だったようである。
何かの読み物を読んだ時にも、明治から大正にかけて、三陸地方は豊かであったという記載があった。
これを読むと、たしかにそうであったらしい。
高村光太郎は、そのあまりにも賑やかな気仙沼には、おそらくは1泊程度しかいなかったようでさる。そうして「釜石行きの船に乗る。」で終わっている。
いまは気仙沼市に合併した唐桑は、それまで「唐桑町」という別の町であった。
その唐桑に、いまも高村光太郎の文学碑が残る。
「黒潮は親潮をうつ 親潮はさ霧をたてゝ 船にせまれり」
高村光太郎は唐桑で下船しているのではなく、御崎を船で通りすぎる際に読んだ歌が石碑となって残っている。
ネットでよくよく検索すると、この「気仙沼」は、昭和6年夏、「時事新報」の委嘱により、三陸地方を約ひと月取材し、同年秋に連載された紀行文「三陸廻り」の中の一つ。
こちらのサイトで全文を読むことが出来ます。
高村光太郎「三陸廻り」
さらにネット検索をすると、気仙沼在住の画家佐藤淳平さんという方のページに「現在的視点その解説」があって興味深い。併せてご覧下さい。
さらにさらにネット検索してみますと、佐藤淳平さんは、私と同じ魚町2丁目の方のようです。たぶん、1〜2分程度のご近所さんであった可能生があります。プロフィールに「森産婦人科」で誕生とありまして、私も同じ病院にて誕生しており、あれ?っと思った次第です。間違えていたらごめんなさい。