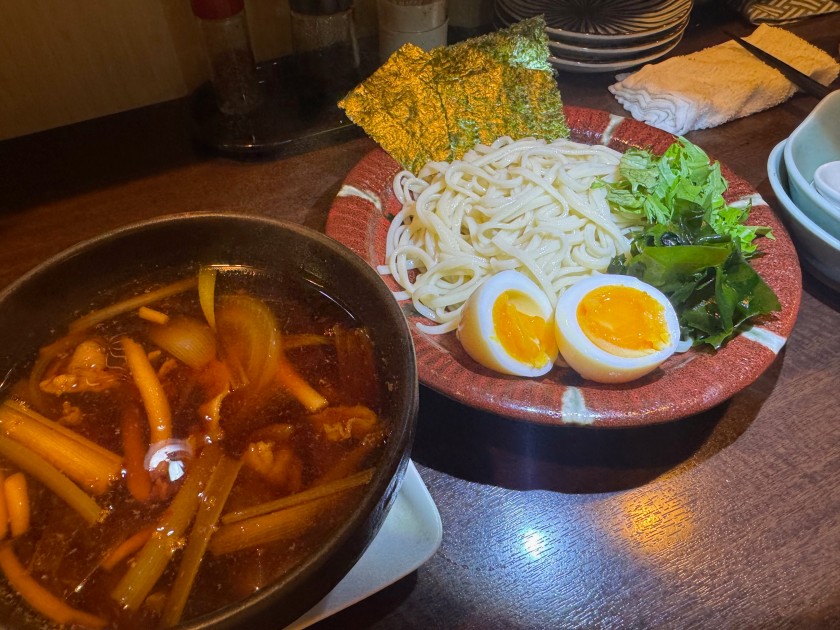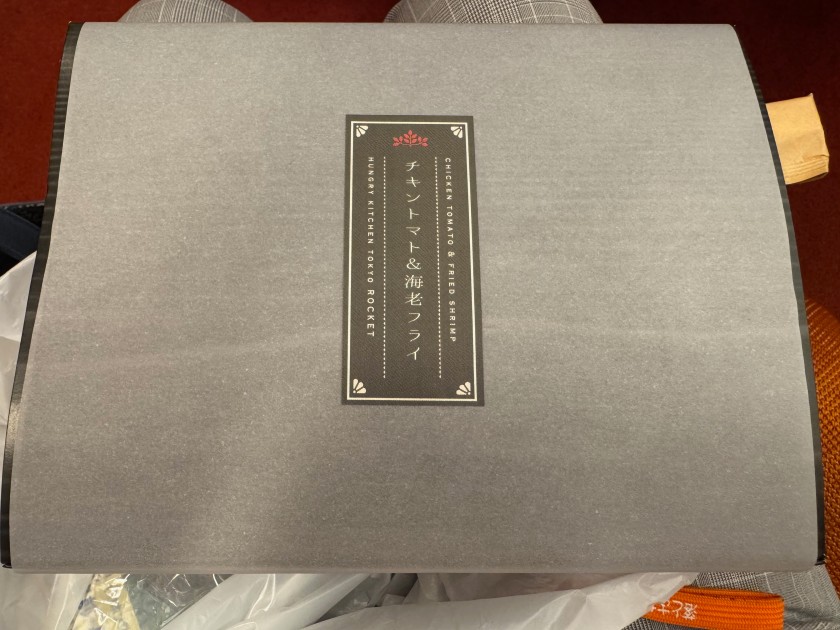「居酒屋いのうえ」さんに行きましょう。「2周年」おめでとうございます!!!

日: 2025年9月18日
歌舞伎座:秀山祭九月大歌舞伎(昼の部)
松竹創業百三十周年・秀山祭九月大歌舞伎です!
地下でお弁当を買って、イヤホンガイドを借りて、ワンピースも1着買って、地上へ。

今日のお席は(桟敷席が取れなくて)1階12列の1番。今日も満席。歌舞伎人気は凄いわ。
今月はAプロとBプロで配役が代わる。今日はBプロ。
通し狂言 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)
竹田出雲・作、三好松洛・作、並木千柳・作
序幕、加茂堤(かもづつみ)
桜丸:中村萬太郎
八重:中村種之助
苅屋姫:中村米吉
斎世親王:坂東新悟
三善清行:坂東亀蔵
イヤホンガイドが説明する。
1746年:菅原伝授手習鑑
1747年:義経千本桜
1748年:仮名手本忠臣蔵 が初演された。
これら3作品を三代名作という。そして、今年、2025年3月、9月、10月に歌舞伎座で上演される。3月も観た。10月も予約している。楽しみ。三大名作を一挙上演するのは松竹創業100周年にあたる平成7(1995)年以来、30年ぶりだそう。
通し狂言とは「歌舞伎で一つの狂言を序幕から大詰まで全幕、またはそれに近い形で通して上演すること、およびその狂言そのものを指す」そうです。
文楽と歌舞伎の違いは、歌舞伎は俳優が話すことだそうで、確かにそうだ。
そんな良い演目なのに、なんてことだ、寝てしまいました。27分という短い舞台だというのに。目を覚ますと美しい舞台に演者達が美しく立っている。また眠る。すみません。
二幕目、筆法伝授(ひっぽうでんじゅ)
菅丞相:松本幸四郎
武部源蔵:市川染五郎
戸浪:中村壱太郎
梅王丸:中村橋之助
菅秀才:中村秀乃介
荒島主税:中村松江
左中弁希世:市村橘太郎
腰元勝野:市川男寅
三善清行:坂東亀蔵
局水無瀬:市村萬次郎
園生の前:中村萬壽
なんてことだ、またまた寝てしまいました。何のために来ているのか。
三幕目、道明寺(どうみょうじ)
菅丞相:松本幸四郎
立田の前:片岡孝太郎
宿禰太郎:中村歌昇
判官代輝国:中村錦之助
苅屋姫:中村米吉
贋迎い弥藤次:片岡松之助
奴宅内:坂東彦三郎
土師兵衛:中村又五郎
覚寿:中村魁春
三幕目はバッチリと起きて、最後まで堪能しました。なんて不思議な現象と、そして悲しい終わり方でしょうか。
菅丞相はやましいところがなくても九州に流される。「伝授は伝授、勘当は勘当」は「師から弟子への教えは受け継がれるべきだが、師に背いた「勘当」という行為は、それとは全く別のものであり、帳消しにはできない、という厳しい現実を示す」。
菅丞相は太宰府へ流されて行く途中、伯母の覚寿(かくじゅ)の館の一部屋に身を寄せている。苅屋姫は一目会ってお詫びをと忍んでやって来るが、覚寿(姫の実の母)に杖で打たれる。すると部屋のなかから「折檻(せっかん)したもうな」と留める丞相の声、しかし部屋に居たのは丞相が自ら刻んだ木像のみ。そして夜も明けぬ頃、やって来た迎えに伴われて菅丞相が出発するが、実は時平方がにせの迎えを遣わして丞相を殺す計略。やがて本物の迎えがやって来ると再び丞相が姿を現わし覚寿は驚く。実は先程連れて行かれたのは木像で、何と魂のこもった木像がまぼろしを見せて丞相を救ったのである。